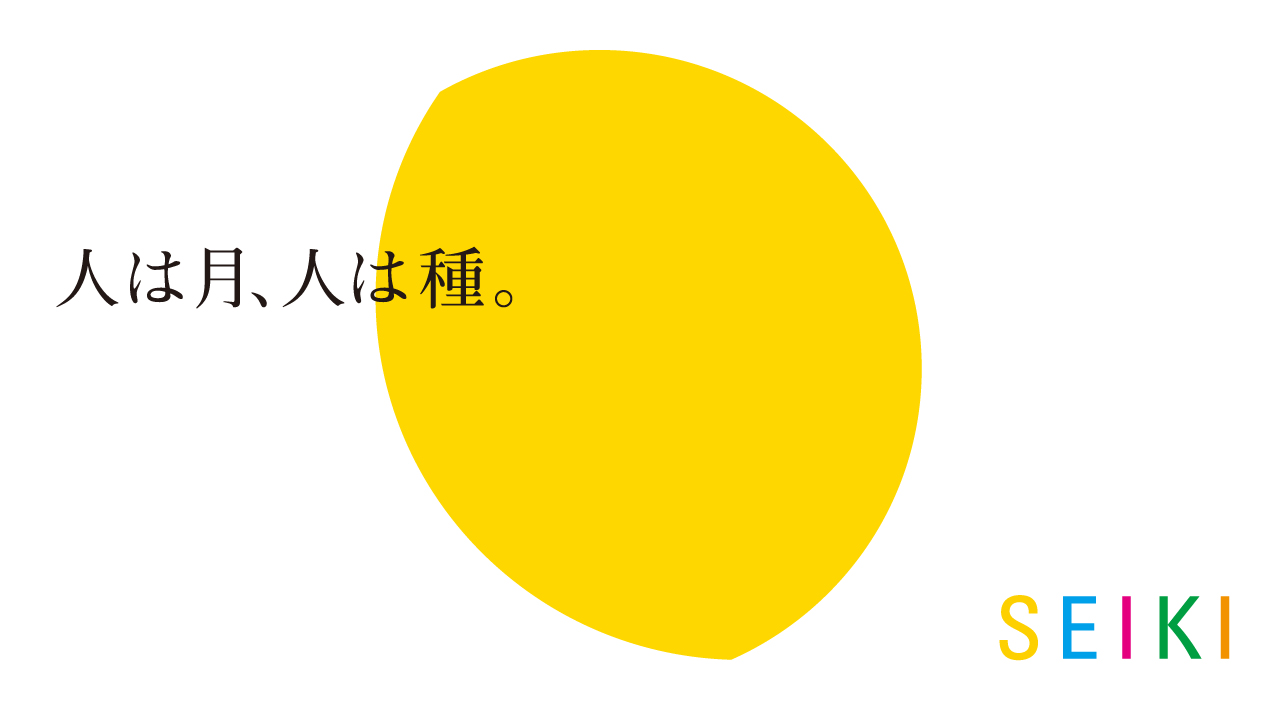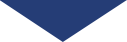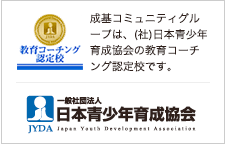成基社員からの
「声」

「メンターとしての自信をもらえた言葉」
田中明綾(成基学園)
昨年度担当していたMちゃんは、「先生、わからない!」とすぐ私を捕まえようとする子どもでした。彼女には実力があるはずだと信じていた私は、「まずは自分で考えてみ!」と突き放していました。その都度拗ねていたMちゃんでしたが、次第に自分で考えて答えを導けるようになりました。
そのころクラスでは、答えが導き出せず苦しんでいる子を見かけるようになりました。そこで、「Mはこの問題できてたやんな?まだできてない子に教えてあげて!」と伝えました。するとMちゃんは、わからないと嘆いている子に対して、決して答えは教えず、「これがこうだとしたら、次どうなると思う?」と自分で考えて答えを導き出せるように教えてくれました。
それが何度か続くと、Mちゃんは自分が解き終わったら終わり、ではなく自ら周りで困っている人を見つけてフォローしてくれるようになりました。
そんなMちゃんに私は、「Mの教え方は本当に上手だよね!ありがとう!」と伝えていました。
そんなクラスでの最終授業日、彼女からありがとうカードをもらいました。そこにはこう書かれていました。
「1年間ありがとうございました。先生の授業をうけて英語がもっと好きになりました。これからももっといろいろな人に英語をおしえてください。」
最後の一文からMちゃんの成長を感じ嬉しく思うのと同時に、自ら考えることの重要さを彼女から教わりました。Mちゃんのこの言葉を支えに、私はこれからも授業を担当し続けます。

「成長を見守る居場所」
桑島理絵(ゴールフリー)
私は社員として入社する前の大学時代はGFでコーチとして勤務していました。
私が2回生の一年間英語を担当していた当時中3のK君という子がいました。彼はクラスでも中心的な存在で、明るい子でしたが、思春期にご両親が離婚されたこともあり、夜中に帰宅したりと荒れはじめていました。
GFには毎日ように通ってくれていましたが、成績は5教科で200点を切っており、授業以外でも何度も彼と面談をし、友人関係や家庭でのトラブルの話をよく聞いていました。そんな状況だったため、何とか公立高校に合格したものの、私は高校に入ってからの生活を心配していました。
時は流れ2年後のある日。たまたま駅で彼に再会しました。彼は高2に、私は社会人になっていました。体が二周りほど大きくなっており、顔つきもしっかりしていました。
「久しぶり!最近どう?」と聞くと、「ラグビー部に入って、毎日頑張ってるで!英語も学年で10番以内に入ってる!」と、当時の彼からは想像できない成長ぶりを聞かせてくれました。
そこからまた2年の月日が流れ、先日のことです。私が自宅近くのコンビニに立ち寄った際、一生懸命働く彼の姿がありました。忙しそうにしていたので、話はできませんでしたが、2年前より更にしっかりした彼がいました。
彼の授業を持っていた当時の私は気づきませんでしたが、気持ちが不安定だったあの中3のときに私や他のコーチ、教室長を含めたGFという居場所があったことで、彼自身が前を向けるきっかけ作りを少しでもできていたのかと今では思います。
彼の益々の活躍に期待するとともに、今関わっている子どもたちにも居場所をつくれるような関わりをしていきたいと思います。

「未来を創る再会」
小幡晃子(TAMランド)
草津市では認可小規模保育事業主を公募され、今回そのひとつを株式会社成基が請け負うこととなりました。認可決定以後、草津市の担当のみなさまにはいろいろとお世話になっております。
私は10年ほど前に成基学園アストロ(長岡京)の教務をしておりましたが、その際にアストロの元園生だったI君は模擬試験バイトやPサポートの講師として働いてくれていました。彼が草津市役所に就職したらしいと噂で聞いてはいたのですが、広い市役所では見つけることができず、もう私の事も覚えていないだろうと思っていました。
2週間ほど前にTAMの幼稚園営業で草津市の幼稚園周りをしていると、ある幼稚園に作業着を着た市役所の方がいらっしゃいました。思わず「I君!」と声をかけました。10年前と変わらないI君の笑顔があったからです。「小幡先生ですよね?僕、市役所の幼児課にいるんです!新しい小規模保育を成基さんがされると聞いてはいましたが、小幡先生が担当なんですか?またこうして一緒にお仕事できるなんて嬉しいです!成基で保育園も始められるんですね。草津市のためにありがとうございます、待機児童を減らしたいと思ってみんながんばってます!」それはもう、その場にいらっしゃる他の幼稚園の先生が驚かれるほど、熱心に再会と成基での保育事業開始を喜んでくれていました。
こんなすてきな元園生とこれからお仕事できる、保育事業の未来が明るく思えた出来事でした。

「志を通して自信を育む」
戸田ほのか(東進衛星予備校)
私は、東進生との関わりの中で、志に関する話をする時間が一番好きです。彼らが何を大切にしているのか、自分のことをどんな人間だと感じているのか、にふれることが出来るからです。しかし、東進に通うのは高校生。いろんなことを経験してきた今、心のうちを明かすことが出来ない子も、少なくありません。そんな彼らにどこまで踏み込んでいいのか、最初のころはよく悩んでいました。
今年の夏、校舎で志ワークをしました。週に1回のグループ面談の時間を使い、2か月にわたって【志とは何か】【自分の中にはどんな志があるのか】を東進生たちにグループで考えさせました。私はある1年生グループと志ワークをしましたが、その中でひとり、自分の思っていることを言えない男の子がいました。理由は、「自信がないから」です。それを聞いた私は、みんなにこう提案しました。「みんなが思っていることを言えるために、全員にとって意味ある時間にするためにどうすればいいかを考えて、ルールを決めよう」と。グループで考えた結果、出た結論は「相手を否定せずに受け止める。否定をせずに意見・感想を言う」です。まさに、【安心・安全な場】が合言葉となりました。
それ以来、その男の子は勇気を持って意見が言えるようになりました。そのことをお母様にお伝えしたところ、「あの子も私自身も、本当に自信がないんです。でも、そういうことを大切にしてくれる戸田さんやグループのお友達がいてくれるのは、とても安心です。」と言っていただきました。後日、お母様から頂いたCSアンケートには『勉強以外の大切なことを伝えてくださり、ありがとうございます。』といった内容の言葉が書かれていました。余計な遠慮をせず、彼らに踏み込むことで、彼らや保護者様の想いに触れられると確信した出来事でした。

「心の奥底にある想いに灯をつける」
伊野麻衣(ゴールフリー)
去年の秋、5教科合計点数130点くらいで入会した中2のYさん。お母さんが地元で飲食店をしている影響で、人懐っこく、「お母さんのお店を継いで常連さんに喜んでもらうこと」と、将来の夢も決まっていました。しかし、勉強に対しては苦手意識だらけ。決してさぼっているわけではなく、「自分はこれくらいしかできひんから」と限界を決めているようでした。そのため、将来の夢はあっても高校の選び方や何のために高校に行くのかがわからず、おいしい料理さえ作れたらいいから、行ける学校で調理コースがあるならどこでもよい、というのが入会当時の彼女の進学に対する希望でした。
彼女と関わっていく中で、彼女の原動力は、自分の頑張りでコーチやお母さん、おばあちゃん、周りの人が笑顔になることなのかな、と感じました。授業の中でできるようになったこと、勉強会での取り組み、テストの点数が思うように伸びなくても、その過程をしっかりコーチと笑顔で承認するようにしました。そうすればするほど、自習時間は増え、宿題をどんなに出されても、笑顔で「やってくる!」と頑張るようになりました。そうなると、結果ももちろんついてきました。
10月の五ツ木模試では、9月に比べて偏差値が10ポイントも上がりました。返却するとすぐに、お母さんとおばあちゃんに写メを送って一緒に喜んでいました。そして少しずつ自信が出てくると、夏までは受け身で高校の話を聞いていたのが、積極的に高校を調べたり、普通科に行って大学進学もありかも、と進学に対しても前向きになってきました。今は、大学でお店の経営について学ぶことを視野に入れ、受験と真剣に向き合っています。
人によってモチベーションの上げ方もそれぞれです。日々の関わりの中で、一人ひとりに合わせた接し方、声掛けがあることを学びました。

「本当にやりたいことを一緒に見つける」
山縣聖奈(ゴールフリー)
Kちゃんは中3の頃からGF生駒教室に通っています。いつも自分に自信がなくて、「絶対無理やもん」が口癖の女の子でした。
そんな彼女が今年で高3になりました。自分に自信がなく、将来やりたいこともなく、進路選択にとても悩んだ1年でした。
興味があることが絵を描くことや服を作ることだったので、アート系の大学・学部を探すも「私なんて才能ないから無理かも」と悩んだり、色んな大学・学部を探しても「やりたいことないのに大学に行っても意味ないかも…」とKちゃんは、否定的な感情から自分の選択肢を狭めてしまっていました。そんな彼女に対して私は「大丈夫だよ、自分がしたいと思えることを探せる大学を一緒に探そう」、「悩むなら最後までとことん悩んで決めていこう」と彼女を承認した上で悩みを傾聴し続けました。
その結果、夏にはある大学の学部でなら自分の幅を広げるために色んなことが勉強できそうと考え志望することを自分の意志で決めることができました。そこからKちゃんは、スイッチが入ったのか毎日自習に来て猛勉強するようになりました。今までのKちゃんにはない気迫がありました。
そして、まずはその大学の指定校推薦を出した結果、なんと合格することができました。指定校推薦では、科目試験がないため、勉強してきたことが直接的に結果に結びついた訳ではありませんが、志望校に向ける強い想いとそこから頑張っていたKちゃんのことを神様は見ていたのかもしれません。
そのKちゃんは、この喜感体験記を書いている今日がGF生駒教室での最後の授業の日でした。「たくさん悩んだ時期もあったけど、だからこそ自分の行きたいと思える大学を見つけることができました、大学でも勉強頑張ります!」と彼女からは力強い言葉を受け取りました。

「未来と自分は変え放題!」
阪口雅弘(ゴールフリー)
私にとって、一番思い出に残っている子どもは、コーチ時代に4年間担当したCくんです。
私はCくんを、彼が中3~高3までの4年間担当しました。
そんなCくんは、今や私が以前にコーチをしていた教室で、コーチをしてくれ、先日のエデュバイトグランプリでは教育コーチング部門でグランプリを取るほどのコーチになっています。
しかし、出会った当初のCくんは、先日のEBGPでの力強いプレゼンをしたCくんとは真逆で、様々な悩みも抱えており、自信のない子どもというのが私の第一印象でした。
Cくんとの4年間の関わりの中で、Cくん自身も私自身も順風満帆に進んだわけではありません。高校受験を前に、中々成績が上がらない彼に対し、「このままじゃあかんで」や「●●をしいや」と怒ることもしばしば…怒ることで、さらに状況が悪循環…
そんな彼に大きな変化があったのは、私自身の関わりを変えてみたときでした。
『●●をさせよう』と彼自身を変えるではなく、「何をしたい?」と彼自身に決めてもらう…コーチングでは当たり前の関わり・あり方であったのですが、私自身の焦りから一番大事なことを忘れていました。
『過去と他人は変えられないが、未来と自分は変え放題!』
この言葉は彼との関わりから私自身が学んだ言葉であり、今、GF膳所の教室目標として、大きく掲示をしております。
そんな私もまだまだ未熟であり、ついつい教室の子どもやコーチに『●●をさせよう』と彼ら自身を変えようとすることもしばしば…
そんなときは、教室の真ん中に掲示しているこの言葉を読み返し、Cくんとの関わりを思い出すようにしています。
これからも、この想いを胸に、教室の子ども・コーチが、未来に向かって、自分の力で切り拓く、活気のある教室を目指してまいります。

「具体的なイメージで行動が変わる」
湯浅大和(ゴールフリー)
Mくんとの出会いは、彼が中学校3年生のときでした。入塾相談の連絡を受け、初めて彼に会ったとき、無理やり母に連れて来られており、不機嫌で一言も話してくれませんでした。彼自身、漠然と志望校を目指していましたが、学校の成績が悪く、学校の先生に受験は厳しいと言われていました。モチベーションも低く、今までテスト勉強を含め、勉強をしたことがないといった子どもでした。
そこで、体験授業で、志望校卒業の先生に担当をお願いし、高校でどのように頑張ったかや大学の勉強内容など、本人の将来を具体的に考えられるような話を盛り込むようにお願いしました。その結果、本人の漠然とした「この学校に入りたい」という想いが本物となり、やる気を示してくれました。
入塾してから、お母様も驚くほど本人の勉強に対しての意欲が向上し、自主的に自習室で勉強するようにもなり、見事志望校に合格しました。担当のコーチを慕い、「自分もコーチのように頑張って勉強する。将来は京都中央のコーチになる!」といったことまで言ってくれるようになりました。
当初は勉強というものに対して嫌悪感を示し、一切勉強をしなかったMくんが、コーチから影響を受け、自ら進んで勉強をするようになり、「自分も勉強が分からない子の気持ちに寄り添い、コーチとして頑張っていく。そのためにも今頑張っている高校の勉強をこれからも頑張っていきたい」と僕に語ってくれます。
こんな風にコーチから影響を受け、前向きに将来に向けて頑張ろうという想いが溢れる教室になれば、素敵なことだと思います。これからも“こんな人になりたい”という憧れの集団の教室であり続けていきます。

「挫折・失敗から学ぶこと」
合志紘美(ダビンチ、ロボ団)
理科実験ダビンチに通ってくれている小2のAくんは、自信たっぷりの男の子。意見を積極的に言い、作業も早い子です。
ある日の授業。課題は「自分で設計図を書き、教室の上まで飛ぶ気球を作る」でした。
紙風船で作って全部燃えてしまう子、材料が重すぎて飛ばない子など、皆結果は散々です。Aくんも初めは色々と挑戦していましたが、なかなか思い通りにいかず、すねて作業の手を止めてしまいました。
実は、この授業の意図は「挫折・失敗を知る」ことです。そのために、この授業ではあえて難しい課題に挑戦します。全員が気球を飛ばすのに失敗した後は、徹底的に失敗原因の洗い出しを行いました。失敗の原因を理解した子どもたちは、最後にもう一度気球作りに挑戦し、成功するところまでやり遂げます。ところがAくんは「どうせ作っても失敗するから」と、唇をかみしめて座っていました。授業の終わりが来てもとうとう彼だけは気球を作れませんでした。
1か月後の授業日、教室に来るなりAくんは「もう一度気球の作り方教えて!」と言いました。彼は一か月間、色んなことを考えて、気持ちの整理をして、この結論に至ったのでしょう。授業後改めて気球作りに取り組み、上まで飛ばした彼の顔はとても晴れ晴れとしていました。それからAくんは、どんな失敗をしてもすねて作業をやめることはなく、原因を考えて根気強く取り組むようになりました。このように今後も、私は子どもの成長する場、諦めずに挑戦する力を育むきっかけづくりをしていきたいと思っています。

「その子にとってのベストを考える」
中井 美砂子(成基学園)
Yちゃんがお母さまに連れられて学園草津の門を初めてくぐった時のことを、今も思い出すことができます。転塾を考えているとのご相談にのり、5年生後半からの入塾となりました。彼女の志望校が私の母校であったこともあり、話をするにつれ心を開いてくれるようになり、6年生で私は彼女のクラス担任となりました。
合格ラインに届く成績も出るようになり、このまま順調に…と思っていた6月、彼女はぱたりと塾へ来なくなってしまいました。実は小学校にも通えていない、とのことでした。門の前まで来るのに、門をくぐったその先へ足が動かないのです。
その後6月から9月の通常授業と夏の講習会をすべて欠席する傍ら、毎日のように電話でのやりとりが続きました。数えきれないほどの面談をしました。家庭訪問も2回行きました。そのたびにYちゃんは辛そうに、「自分を変えたい」と繰り返しました。それでも通常授業には復帰できず、受験すること自体を諦めかけていました。
しかし私は受験はするべきだと考えていました。「合格」という自信を得て、彼女の今の状態を誰一人知らないような、面倒見のいい私立へ行くことが、彼女を変える術だと感じていたのです。
そこで、Yちゃんとお母様、そしてGFの教室長を交えて四者面談をしました。思いを伝え、候補になりうる学校を提案しました。そして、GFへの移籍を勧め、彼女は自分で決断をしました。残りの半年を2教科に絞ってGFに通い、努力を重ねたYちゃん。あれほど足が止まってくぐれなかった門を勢いよく通り過ぎ、満面の笑顔で「受かった!」と報告に来るまで、あっという間だったように思います。
デスクに大切に貼ってある「先生から勇気と自信をもらいました」という彼女からのお手紙は、今日も私に勇気と自信を与え、そして「その子にとってのベストを考えろ」と語りかけてくれています。

「最後まで寄り添い続ける」
出村 優紀美(ゴールフリー)
今年の春に、無事、第一志望校に合格したT君の話をさせていただきます。
中3の夏、しかも夏期講習も残すところあと10日ほどというタイミングで入会したTくん。入会当初はとても意欲的に、授業にも宿題にも取り組んでいました。
しかし夏休みが明け、学校が再開し、これまでのリズムが戻ってくると、徐々に彼のやる気が減退していく様子が見え始めました。机間巡視時に話をしてみるものの、その時だけの気持ちの切り替えで終わってしまい、続かない、といった様子でした。
そんなころ、夏休み明けに受けた模試結果が到着したので、その返却も含め、Tくんと面談をしました。「最近、勉強はどう?」と尋ねたところ、「わからんとこが多すぎて、やる気出えへん。やってももう無理や。高校行けへん。」と、笑いながら言っていましたが、しばらくずっと俯いたままでした。
私は、高校で何をしたいのか、わからないところはどこなのか、コーチにリクエストがあるかを聞きながら、Tくん自身と改めて目標と現状を確認していきました。模試の結果も散々であったので、なかなか笑顔は見られませんでしたが、授業の日は1時間早く自習に来ること、授業後も1時間自習することを、約束しました。
面談の翌日、彼は授業がないにも関わらず自習にやってきました。自分で決めたから、と、面談時には見られなかった、すっきりした顔が見えました。しかしその行動も、2週間ほどでぱったりと止まってしまいました。
その後も自習に来なくなったタイミングで話をすることを繰り返しながら、公立高校の受験が迫ってきました。志願変更を学校に提出する前日、Tくんと、どこに出願するのかを話し合いました。安全圏の学校に志願変更するか、私学に行くかもしれないことを承知でチャレンジするか。内申が足りていない状況で、得点力も安心して送り出せる状態ではない彼を、チャレンジさせて良いものか、私自身も悩みながら、様々な資料も見ながら、可能性を含め話していきました。
結果、志願変更せずに、出願することとしましたが、少しでも可能性を高めるために、毎日自習に来るようにスケジュールを立てました。今まで、自習といってもなかなか続かなかったTくんですが、受験前の最後のスケジュールは、見事やり遂げてくれました。
卒業式の時にお母さまと話をしたのですが、「本当に最後の最後で変わってくれたと思う。先生が、第一志望も、この子のこともあきらめずに見てくれて、本当にうれしかった」と言っていただきました。Tくんの変化と、合格と、お母さまのお言葉と、嬉しく、かつ有難いものを一度にたくさんいただきました。今年も多くの受験生がいますが、一人一人、しっかりサポートをしていきたいと思います。

「子どもたちの「無限の可能性」を信じて」
柴田 大佑(成基学園)
成基学園で子どもたちの受験指導に携わって、丸14年が経過し、今年15年目に突入しました。多くの子どもたちが大学を卒業し、社会へ出て活躍をしてくれています。
その中の1人に、ギャラクシーで指導した女の子がいます。中々手のかかる子で、何度となく勉強の姿勢について厳しく指導しました。何とか中学受験では志望中学校に進学し、順調に頑張っているという報告を受けて、そこから6年…。もう数年前になりますが、ちょうど大学進学の時期に今後の進路について、教室まで報告に来てくれました。
「実は、色々考えて、大学に進まへんねん…。ダンスの道で進んでいきたいねん。先生、ごめんな…。あんだけ色々やってくれたのに…。」と涙を浮かべながら話す彼女。当然、親御さんとの間では、大学進学についてかなりの話し合いはあったと思います。私自身も「ダンスで生活していくよりも、大学に進んで安定した職業の方が…」という考えが頭をよぎったことも否定できません。ただ、それ以上に、自分がやりたいこと、それに対して全力を尽くしたいと言葉にすることができる彼女がとてもまぶしく感じられました。
現在彼女は、枚方パークやUSJなどのパレード、様々なアーティストのライブでダンスを担当する他、劇団に所属し、演劇にも力を入れています。
子どもたちが、自らの行動をもって証明してくれる「無限の可能性」を感じるこの仕事に誇りをもって、今日も元気に登園してきてくれる子どもたちに関わっていきたいと思います。

「子どもの成長を実感できる仕事」
矢幅 史祥(ゴールフリー)
今日は中1のWさんのお話をさせて頂きます。Wさんはいつも明るくて元気いっぱいの生徒で、授業も一生懸命に取り組んでくれる子です。ただ、精神的に好不調の波があって、去年は数か月学校に行けていない時期がありました。
そんなWさんが今回初めて中学校の定期テストを受けてきました。プレッシャーにそんなに強い子ではないので、テストは怖いなと若干思っていましたが、テスト結果は散々で、かなり本人も落ち込んでいました。
以前の不登校の経験から、また精神的に落ち込んでしまうかもしれないと不安になり、お母さんともお話しながら対策を考えました。その後、本人と話すことになったのですが、やはり落ち込んでいました。
Wさんのマイナスな考えをフォローすることで次に向かって頑張ろう!という気持ちを持たせるように話していったのですが、以前と違ったのは、教室に掲示してある志シートを指さしながら、「私は小学校の先生になるという夢があるから頑張る!」という前向きな言葉でした。
正直とても驚いたと同時に、成長しているなと実感した瞬間でした。
自分は、こういった人の成長を目の前で実感できる、とても楽しい仕事を選んでいるのだと再認識しました。コーチも含め、教室に関わる全ての人が、自分の目標に向かって前を向いて進んでいける環境を、教室の責任者としてこれからも作っていきます。

「不合格を乗り越えて」
野口 由真(成基学園)
中3生のHくんは、堀川高校探究科を第一志望に、コツコツ真面目に勉強に取り組んでくれる子どもでした。
偏差値も順調に上がっていき、最後には見事合格を勝ち取ってくれました。しかしながら、その道のりは、決して平坦なものではありませんでした。
受験校を決定する最終面談。日進の偏差値も、目標とするところには到達しており、各メンターからの所感も特に問題がなかったので、併願校の相談が中心になるだろうと思っていました。
予想通り順調に話は進み、「もう終わるけど、最後に何か聞きたいことや不安に思っていることはない?」と軽い気持ちで本人に尋ねました。すると突然、Hくんの目から涙が零れだしました。「前みたいに、落ちるんじゃないかと思うんです。」「どれだけやっても不安なんです。」「もっと難しい問題集を探して、やった方がいいんでしょうか。」と、抱えていた不安を少しずつ話してくれました。彼は中学受験で不合格となり、そのまま中学部へと進級してくれた子どもでした。中学1年生の時から真面目に勉強に取り組み、周囲から見れば、とても順調そうに見えていた彼。その彼の心の中には、大きな不安が常にあったのでした。「やってもやっても不安な気持ちはわかる。でも、これまで努力して着実に成績を伸ばしてきた自分のことをもっと信じてあげよう。」そう伝えると、彼は涙ながらにうなずいてくれました。「堀川に合格して、"あの時不合格になってよかった"って思えるような結果を、自分の力で掴み取ろう。あなたならできるよ。」そう伝えて、その日の面談を終えました。それからの彼は、迷いが吹っ切れたように、ただひたすら目の前の勉強に打ち込んでいきました。
合格発表の日、報告をくれた彼は、もう泣いてはいませんでした。「景色が違って見えます。ここまで頑張ってこられて、本当によかったです。」「本当におめでとう。…どう?中学受験、不合格になってよかった?」そんな私の質問に、「はい!」と晴れやかな声で答えてくれました。不安に打ち勝ち、自らの力で望む未来を掴み取ったHくん。きっと彼はこれからも、自分の力で一つずつ困難を乗り越え、前に進んで行ってくれるだろうと思います。

「自分で考えて行動する」
北 陽子(ゴールフリー)
本日は中3のAさんについてお話したいと思います。
Aさんはこの4月からゴールフリーに通い始めました。Aさんは入会当初から志望校が決まっており、勉強も好きで、意欲はとてもあるお子さんです。しかし、意欲がある一方で学習の計画性が欠如していることで得点に繋げられていないということが課題でした。
勉強しようという思いはあるものの、提出物などがぎりぎりまで終えられず、本当の意味でテスト勉強をするということが出来ないままテスト当日を迎えるというのがAさんのテスト前のパターンでした。
そこで入会面談の時点で、1学期中間テストは、テストの1週間前には提出物を終わらせられるようにしようと約束をしました。そして、テスト1か月前からは授業で来るたびに課題を終わらせる約束について確認しました。
しかし、中間テスト前、授業を受講している科目は1週間前に課題をやり終えられたものの、受講外の科目は提出物をテスト前日まで終えられず、その科目のテスト勉強はできず、それぞれのテスト勉強への頑張りが良くも悪くも反映された結果が返ってきました。
その後、テストの振り返りをした際に、「自分では今回の点数どう感じる?」と質問すると、Aさんは、「今回の結果は満足していない」「次は絶対テスト1週間前に提出物終わらせる! 受講していない科目も含めて5教科で400点越えたい!」、そんな風に話してくれました。
その話の通り、中間テスト前よりも計画的に学習を進めるAさんの姿がそこにありました。さらに、以前はテスト勉強を見越して、宿題を多めに出すと渋っていたAさんが、期末前には「もっと出してほしい」と自分から言うようになりました。
そんな風に取り組んだテストの結果は、まだ実は返却されていません。しかし、目標に対して自分が行動できていたか、客観的に振り返り、違いを作るべく行動を変えたAさんに、教室の従業員全員が、子どもたちに常に目標を意識させることや自分で考えてもらう機会を作るべく行動していくことの重要性に改めて気づかせてもらいました。Aさんのテストの結果を楽しみに待ちつつ、今後も教室に通ってくださるすべてのお子さんに対して、自ら考え、行動してもらえる機会を作るべく、関わっていきます。

「一期一会」
駒村 英司(成基学園)
昨年度と今年度と2年連続して異動となっており、子どもとのつながりが希薄になっていると感じておりました。先日、以前の勤務先の卒園生が教室に来てくれ、大学合格の報告をしてくれました。 卒園した校舎に行ったところ、私が異動となっていることを聞き、わざわざ足を運んでくれたのです。
その卒園生の弟くん(彼も卒園生)の近況を含めていろいろ話をしてくれました。高校でもいろんなことがあったとは言っていましたが、成基学園で学んだことのほうが大きく、多くの時間を学習に割く必要が出てきた大学受験においても、成基学園での経験が、「自分はやったらできる」との自信を持って取り組めた原点である、だからこその合格であると言っていました。
子どもとのつながりが希薄になっていると感じながらの子どもとの関わりでは、今、担当している園生の数年後にとって、大変に申し訳ないことをしているのではないかと反省しました。直接、授業を担当していたのは一年だけであったのに、その場面での関わりが園生の自信を高めることができるのです。
今回の一件を受け、異動が続いたとしても、子どもにとっては大きな一年であり、本当にかけがえのない時間を預かっているのだと真摯に受け止め、新たな力を得られた気がいたします。
一期一会を大切に、業務に専念いたします。ありがとうございました。

「親子の想い」
中西 朋文(ゴールフリー)
今年4月、高校2年生の男子生徒Y くんの入会相談対応でのこと。
「2年生に上がり、自分自身での勉強だけでは限界を感じはじめたことから、通塾を決意し、他塾を含めていろいろと検討することにした」というのがYくんからの第一声でした。
苦手科目のこと、将来目指すもの等、色々と会話を重ねた後、本人が最も気になるという数学の体験授業を行いました。
授業後の会話において、授業前とはまた違ったYくんの目の輝き、前向きな姿勢を強く感じたこともあり、コーチや僕らとぜひ一緒に頑張ってみようと声をかけましたが、「授業料のこともあるので、一旦家で相談してきます」と一転、少し曇った表情に見えたのを覚えています。
翌日、Y君のお母様より、今から教室へ伺いたいとの連絡があり、面談を実施することになりました。
昨夜家に帰ってY君が「お母さん、いくつか塾を見てきたけど、ゴールフリーに行きたいって思った」「週1で考えていたけど、週2回の授業と自習室でがんばりたい」「授業料の負担が大きくなってしまうけど、お願いします」とご両親に頭を下げて話したそうです。
その後、お母さんと会話を進める中、週3回のカリキュラムでスタートすることに決定。「久しぶりに真剣な眼差しの息子を見て、嬉しくなりました」「やる気になった息子を応援したいし、整った環境で勉強してくれるなら安心」「プラス1回は息子へのプレゼントの意を込めて」とのこと。 「思春期ということもあり、普段は口数が少なかったり、言葉づかいが悪かったりと色々とあるんですよー」とも話されていましたが、心にある親子それぞれの想いに胸を打たれました。
そして同時に、その想いに応えるべく責任を持ってお預かりし、サポートしていくことを心に刻んだ瞬間でもありました。現在Yくんは、体験授業時に彼の目の輝きを引き出したコーチとともに苦手分野を克服しながら、一歩ずつ着実に歩みを続けています。これからも、彼に寄り添い、真摯に向き合っていきます。

「言葉の重み」
黒瀬 貴士(成基学園)
今年大学1回生になる何人かの子たちが進学先を報告するために会いに来てくれました。みんな自分の夢を追いかけて進学先を決めていました。小6の時には考えられないぐらいしっかりしていたことをうれしく思いました。
その中の一人にK君がいました。彼は小6の時、第1志望の大阪星光に不合格。第2志望の明星に進学しました。明星でも中1・中2でなかなか思うように成績が取れずに相談に来たことが何回かありました。その時はいろいろとアドバイスをしましたが、その後は会うこともありませんでした。その彼が、「ぼく、アメリカの大学に行きます」と報告してくれました。本当に驚きました。アメリカの大学に進学しようと思ったのは、「先生が、小6の時に『世界の大学はすごいぞ』と言っていたのが頭に残っていたのもある」と言ってくれたのにさらに驚きました。自分が何気なく発した言葉が彼の中にそんなに強く残っていたのかと恐怖に近いものを感じました。子どもたちに話す内容や伝えるときの言葉が子どもたちに影響を与えることを自覚しないといけないと思いました。彼はこの6月にアメリカに向けて日本を発ちます。そこで私の想像もつかない経験をすると思います。
今私の目の前にいる子どもたちにもいろいろなことに興味を持ってもらえるように、そして失敗を恐れずにチャレンジしてもらえるようにいろいろなことを伝えていきたいと思います。

「挑戦する心を育む」
舩越 麻那実(ゴールフリー)
去年の冬、中学1年生のM君の面談を、お母様と三者で実施しました。
夏からの入塾ではあるものの、全く上がらない成績にお母様も本人もすっかり自信をなくしていました。野球部で忙しく、しかし1年生にして周囲から頼られる誠実で努力家なM君をなんとか助けたいと思いました。
まずは彼が最も苦手だった英語から取り組みます。毎週自習時間を決めて、計画をたてて一緒に取り組みました。目標は、英語の3学期中間で8割獲得しようねと話をしました。
そして結果は、86点でした。今までどの科目でも80点以上をとっていなかったM君は、それはもう嬉しそうに報告しに来てくれて、私自身も非常に嬉しかったことを覚えています。
「先生、僕は英語の勉強方法がわかったから、これからは自分でできそう」
と、自信に満ちた顔で教えてくれました。お母様からも、
「これが本人の自信に繋がったと思う」
と、喜んでいただけました。
今回は何が良かったのか、テストが終わって担当コーチと振り返りを行いました。まずは勉強内容が明確だったこと。そして、やっても点が取れないから自信がなくなっていたところに、社員やコーチが寄り添って一緒に挑戦できたこと、だと思いました。
彼だけでなく、すべての生徒に自信を持って挑戦していく力をつけて欲しいです。そして、達成できたときの喜びを感じて欲しいです。私は、今後もこのような想いで生徒と関わり続けます。

「子どもの幸せのため、責任を持って行動する」
堀池 夏樹(ゴールフリー)
チャレンジ合宿で出会ったKちゃんの話をしたいと思います。1日目の夕方。「帰る。お母さんが辛かったら帰ってきていいって言った。」Kちゃんはホームシックで泣いていました。
しかし、たくさん話して泣いた後は、すっかり元気になり、ホームシックは解消したかに見えました。ところが、次の日の朝も夕方も、泣いています。
不思議に思って話を聞くと、携帯電話でこっそりお母さんと連絡をとっていた事が分かりました。頑張ろうとするも、携帯電話には大好きなお母さんからのメッセージ。彼女が弱くなる原因でした。彼女にとって、お母さんが良いと言ってくれた事はそれ自体がルールとなります。とはいえ、今のKちゃんにとって良い状況とは思えませんでした。
その夜。また泣いているKちゃんと話す為に外に行きました。星を眺めながら話したのは「携帯、私に預けない?」という話。Kちゃんの不安そうな顔。私はお母さんと作ったルールの変革を投げかけました。次の日の朝。「預かってて。頑張ったってお母さんに言いたいから。」そう言った彼女は涙でぐちゃぐちゃなのに、笑っていました。怖いのに決意した、そんなKちゃんを恰好良いと思いました。
「改善」、「変革」の前提には既存の物の存在があります。それは、その人にとって凄く大切なものかも知れません。それでも、変革がその人の為になると感じたなら、行動に移さない理由などありません。たとえ初めは理解してもらえなくても、たとえそれが自分にとっても大変で辛くても、大切な人たちが幸せになる可能性があるのなら、責任を持って行動に移す。これを誠実と言うのだと思います。

「任せることが大きな成長につながる」
森川 賢一(ゴールフリー高等学院)
ゴールフリー高等学院ではグループワークとして校外学習を実施しています。これは5~6名1グループで校外に出て散策や作業等の活動を行うもので、校外学習の前に事前学習というものを行っています。
高等学院に通っている子どもの多くは人間関係に不安を抱いていて、将来社会に出た時に集団の中で生きていく力を身につけてもらいたいという思いで開校当初から継続して行っています。
グループワークをしてきて気付いたことは、我々大人が細かい指示を出すのではなく、方向性を示すだけにとどめることが大切だということです。子どもが考える際に自由度が高ければ高いほど、グループの中に自然とリーダーができ、話し合いに活気が出てきます。
以前は10名にも満たないことがあった校外学習も、現在では30名を超える参加者が集う時もあります。そして嬉しいことに、子どもの方から、「普段の学校生活でも各学年でリーダー制をつくろう。その方がみんなが話ができるようになるから。」と提案してくれるようになりました。
ゴールフリー高等学院の子どもはみな、一度は不登校を経験しています。ただ、ここに来てからの成長はすさまじいものがあります。全員が将来社会に出て立派に生き抜いていけるよう、これらも全力でサポートしていきます。

「毎日の生活に活かす学びを伝える」
井上 美栄(TAM/SSJ)
私は小学低学年向けコース「SSJ」の国語を担当しておりますが、その中で一つ気づいたことがありました。それはSSJの国語カリキュラムは国語として学んだ事を勉強にとどめず、生活に活かす学びをしているということでした。
子どもたちは何のために勉強するのかということをいつも考えています。こんな宿題多くて、漢字もいっぱい勉強して、算数も難しくて、テストしても点数とれなくて。その迷宮にはまればはまるほど何のために今苦しいのかわからなくなってしまうと思うようです。
SSJの授業では、音読や文章の読解を通して文章を書くことの意味を伝えています。そして、「志カ-ド」や「保護者の日カ-ド」や「親への感謝状」などで自分の思いを表現してもらう機会を作っています。そういう体験を通して、自分の思いを伝えるために文章というものがあり、いろいろな人の文章を読み、理解することで自分の考え方が変わっていき、それを誰かに伝えたくなる。自分の事を知らない人にも伝えていきたくなるから国語の勉強があるのだ、と子ども達自身が感じはじめています。
ありがとうカードも、字は綺麗ではないものの、とても心のこもったものが書けるようになりました。ある子が小学校の担任の先生にありがとうカードを書いたので、たまたま小学校へ行った時に私からその先生に直接お渡ししました。担任の先生がすごく喜んでくれたと報告してくれました。勉強を通して子どもたちが生きていくための本当の学びを伝えていくことができたらと思って毎回の授業にどきどきしながらわくわくしながら楽しく頑張っています!

「グローバル社会で生きるために大切なこと」
大道 式子(成基学園)
昨夏、中2生対象の夏期合宿の企画・運営を担当させていただきました。
今年の中2合宿では「Diversity(ダイバーシティ):多様性」をテーマに据え
- 外国人スタッフと積極的にコミュニケーションをとる
- その中で、世界には様々な文化や価値観があることを学ぶ
- 文化や価値観の「違い」に優劣はなく、全てが尊重されるべきものであることを学ぶ
- その「違い」を価値として活かすにはどうすればよいかを考える
の4点を子どもたちに体験してもらおうとカリキュラムを組みました。4日間の合宿を通して、自分とは違う考えや価値観を尊重し、双方が納得できるものを生み出していくことの難しさ、そして大切さを、子どもたちは学んでくれたと思います。
合宿の後しばらくして、参加してくれた子どもの保護者様とお話をする機会がありました。「中2合宿は本当に楽しかったようで、帰ってきてから色んな話をしてくれました。特に、外国人の先生のお話が刺激になったようで、『俺もがんばる!』と言っていました。勉強に対するモチベーションが上がったみたいです」と仰ってくださり、とても嬉しかったです。
このような「学び」は受験には直接結びつかないかもしれませんが、グローバル化が進む中で、世界で活躍できる人材になるためには不可欠です。
そして、自分とは違う考えや価値観に触れることは、改めて自分の夢や将来について考えるきっかけにもなるはずです。
SCGには子どもたちの将来を考えた学びを提供するコンテンツがたくさんあります。これらのコンテンツをより充実させ、子どもたちの心に火を灯すサポートをしてまいります。

「日々の“仕掛け”が、学びの心に灯をともす」
魚住 誠(成基学園)
成基学園では、毎週のショートテストをクラス内にランキング掲示しています。私のクラスでも、毎回、ショートテストを返却したらそのランキングを教室内に掲示しています。ランキングが掲示されると、子どもたちは自分のテストを握りしめてランキング表の前に集まってきます。
先日も小学4年生のクラスで、いつも通り掲示をすると、普段おとなしいKちゃんが、ランキングに載った自分の名前を見て、「うわー、初めて名前ある!!」とはしゃぎ始めました。友達が、「すごいねー、よかったねー!」と声をかけるとKちゃんは、「こんなんあるから塾ってやる気になるし、勉強もやりがいあるよねー!」と答えていました。
私にとっては何年もやっているランキング表ですが、Kちゃんの一言がとてもうれしく、当たり前と思ってやていることが子どものやりがいにつながっていることを誇りに思いました。子どもたちが前向きに、自主的に学ぶ様々な授業を展開すること、ランキング表のように当然のようにやっている「仕掛け」を増やすこと、それが今の自分の生きがいだなと改めて感じました。
残念なことに、Kちゃんはまだその1回しかランキングには載っていません。しかし、Kちゃんは、今でも、「次は載るから!」と胸を張って勉強しています。子どものやりがいややる気を、今以上に盛り上げていく、そんな「大人」になろうと思います。

「自分を支えてくれる保護者のありがたさを噛みしめてほしい」
城下 あい(東進衛星予備校)
東進では毎年、大学入試本格スタート直前である1月上旬に、高3生にむけてセンター出陣式を実施しています。
その際、私はセンター前最後の「宿題」を出しました。それは、センター当日に家を出る前に、送り出してくれる保護者の方に「今まで勉強させてくれてありがとう。頑張ってきます。」と言って出発しなさい、ということでした。
「当日みんな以上に、お家の方も緊張されていると思います。でも、みんなが少しでも結果を残せるように、当日の準備に気を使ってくれたり、当日のお弁当に嫌いなものを入れないようにしてくれたりと、直接声には出さなくても一番の結果を出せるように応援してくれています。だからこそ、ちゃんと感謝の言葉を口にしてから出発してください。」
最初にこの宿題を出したとき、やはり思春期真っ只中の高校生ですので、照れもあり教室がざわめきました。しかし、私が真摯な態度で伝えていると次第に顔色が変わり、最後は全員が真剣な表情で聞き、自分の中に落とし込んでくれているようでした。大人と子供の狭間にいる高校生ですので、普段は生意気なことを言ったり、強気なことを言ったりしていますが、心の底では自分の周りにいる人々に感謝の気持ちをもちながら勉強しているのだなと実感した出来事でした。
これからも、私自身が彼らに尊重と信頼の心を持って接していきたいと思います。

「子どもと保護者の“心の懸け橋”になる」
和田 美知栄(成基学園)
10月、これからが高校入試の追い込みだという時に、A君は学園を離れることになりました。勉強への意欲を無くし、都合のいい言い訳をし、時には嘘もついて、受験生だという現実に向き合えなかった彼を、一番許せずにいたお母さんとの関係に溝ができてしまったからです。
「もう一度ちゃんと息子と向き合いたい」といって、自分が受験勉強に付き合うことを決めたお父さんが、本人を連れて最後のご挨拶に見えました。私は最後まで一緒にがんばれなかった申し訳なさもあり、彼のことを本当に愛してくださっているお父さんを前に「こんなありがたい家族は他にはないよ」と泣きながら伝え、その後は時々彼の家に電話をかけ、お母さんと彼の溝が少しでも埋まるようにそれぞれと話しをすることを続けました。
それから4カ月、まもなく県立の一般試験だというある日、A君から電話がありました。「先生、作文見てほしいから明日行ってもいいですか?」ずっと勉強に消極的であった彼が初めて自分の意思で動いてくれました。自分で「成基に行ってくる」と言い、家を出てきたようでした。書き溜めてあった4本の作文は、何度も消した跡があり、彼の「受かりたい」という気持ちを表しているようでした。やっと、彼の心に「未来を見る」火が灯ったのでした。
合格発表の日。本人とお母さんから連絡をもらいました。「合格しました」という彼の声を本当に幸せな思いで聞きましたが、それ以上に嬉しかったのは、お母さんにお電話を替わってもらった時、「合格掲示を見た後、Aが『お母さん、ありがとう』」って言ってくれました」という言葉を聞いた時です。私たちの仕事は時に、家庭の様々な事情にも入っていかなくてはならないことがあります。親の思い、子の思い、辛いほど感じることがあります。けれど、受験を通して、私たちの存在がその少しのボタンの掛け違いを直したり、心の橋をかけたりできることがあります。
本当に微力ではありますが、このような瞬間に立ち会えると、自分自身も親や家族に心から感謝をし、自分の仕事、存在に生きがい、やりがいを感じることが出来ます。人と創っていく、人を創っていく仕事に恵まれたことに改めて感謝しています。

「親への感謝」
橋本康子(成基学園)
私の教室では、入試の直前に「入試激励会」を実施しています。
当日までの過ごし方や入試当日の注意事項、合否の連絡など事務的な事を伝え、メインは、各メンター・教務から激励の言葉を送り受験生としての気持ちを高める場にしています。私が毎年必ず伝えることは「入試の日にお父さんやお母さん、おうちの方に感謝の気持ちを伝えてほしい。」ということです。中学受験をさせてくれてありがとう、成基学園に通わせてくれてありがとう、送り迎えをしてくれてありがとう、お弁当を作ってくれて(届けてくれて)ありがとう…。とにかく、無事に受験という日を迎えることができたのは、決して自分だけの力ではなく、おうちの方をはじめとしたみんなを応援してくれている人たちのおかげであることに感謝し、言葉にして伝えてほしいとお願いします。
K君は、授業に集中できなかったり、宿題を忘れたり、やってきたとしてもあまり丁寧に取り組めず字も乱雑、何とかして楽にやり過ごそうとする傾向のある子でした。小4から成基学園に入園してくれていましたが、当然成績は芳しくなく、お母さまからは何度も何度も退園の相談を受けました。私はその都度、「信じて見守りましょう。お母さまがしんどくなった時はいつでもお電話を下さい。直接話をしに来てください。」と励ましてきました。K君には「お母さんが一生懸命応援してくれていることを忘れずに頑張ろう。」と言い続けました。
そんなK君も6年生となり、ほんの少しだけやる気を出してきましたが、相変わらずルーズな態度が見受けられ、取り組みも成績もお母さまの期待するレベルには程遠い状態が秋口まで続いていました。結局、合格の可能性が低いまま受験した第一志望校は不合格。望みをかけた第二志望校受験の入試激励は私が担当することになりました。
早朝、入試会場で待っていた私を見つけたお母さまはすぐに涙目に。「本当に大変な思いをして入試を迎えました。たくさんたくさん泣いてきました。でも、〇〇中学の入試の朝に、Kが、お母さん、今まで僕を応援してくれてありがとう。不合格になるかもしれないけど頑張ってきます。と言ってくれた時、涙がボロボロ出てきて止まりませんでした…。本当にうれしかったです。先生のおかげです。何度もやめさせようと思ったけど、本当に成基学園で良かった。第一志望は落ちたけど、合否なんかもう関係ないです。本当にありがとうございました。」と泣きながら言ってくださいました。聞けば、反抗期も重なってお母さまの注意にあからさまに反抗し、自宅では大声を上げたり、口もきかなかったりすることもあったようでした。
力及ばず、第三志望校に合格し進学することになりましたが、入試の朝、お母さんに最高のプレゼントとなるありがとうの言葉を贈った彼がその後初めて登園した日、私は無言で彼の頭をくしゃくしゃにしてやりました。

「言えない想いをくみ取る」
細谷太郎(ゴールフリー)
今日は現高1生のYさんのことを書かせていただきます。 精神的に大人で自己管理ができる、しっかり者。それが彼女に対するコーチの評価であり、お母さまも「すべてを任せています」という態度で接しておられました。
高校受験の志望校が話の中心となった昨年の冬の面談でも、彼女は自分の基準を持って、しっかりと選択をしていました。決して楽観はできないけれど、実力を出せれば比較的に楽に合格できるだろうという状況でした。しかし、本番が迫るにつれて彼女の表情は曇っていきました。気になって面談室に呼んで、話をきいてみました。
最初は当たり障りのない会話でしたが、だんだんと彼女が感じているプレッシャーの大きさがわかってきました。「みんなYさんをしっかり者といっているし、Yさんなら絶対に大丈夫、大丈夫と言ってくる…お母さんだって何も心配していないと言う。でも、本当はとっても不安だし、全然大丈夫じゃない。そして、それをどこにも出せない」。自分にはそう見える、と感じたままをゆっくりと伝えました。
結局Yさんは泣き出して、そして、泣いたことを悟られないように面談室を出るまで、かなりの時間がかかりました。事の経緯をお母さまにお伝えはしましたが、本人には内緒にしてもらいました。
後日話を聞いていくと、原因は英語の長文に対する不安にあることがわかりました。点数はとれていましたが、賢いお子さんでしたので、自分が理解できていないことは自分が一番わかっていたようです。 コーチにこの件をシェアし、粘り強く読解練習をしていきました。とにかく自信をもってもらうように声掛けを続け、「できるようになる」と繰り返し伝えました。
結果は合格。周りからみれば、普通に合格という印象だったでしょうが、本人には弱い自分と向き合った大きな成果だったと思います。
彼女は現在もGFに元気に通ってくれています。生徒の心の変化を見過ごさないように、しっかりと生徒の顔を見ていきたいと思います。

「子どもの中にある答えを引き出す」
上田周平(成基学園)
私が担当している5年生のYくん。彼には図や式を省略するといった怠け癖がありました。しかし、算数が好きだったり本人の素質もあって、最初は概ね優秀な成績でした。ただ、後半からは問題も難しくなり、“出来るだろう”あるいは“何とかなる”という慢心から成績は大幅に下がりました。
自信のあった算数で過去最低の結果が出た事にショックを受け、すぐに私のもとへ来ました。何の為に受験するのか。入学後にどんなことがしたいのか聞くと、彼は目を輝かせながら野球の事をとても楽しそうに話してくれました。ここから先、何が必要かを聞いてみると途中式や図をしっかり書いて、入試に向けて難しい問題にも取り組んでいくことが大切だと、自分で答えを導き出してくれました。
この日を境に図や途中式も自分から書くようになり、今まで多かった暗算が減りました。また、分からない問題や難しい問題があると休み時間でも取り組んでいました。一時は落ちた成績も大幅に上がり、オープンテストでは偏差値60以上、洛南オープンでもベスト10に入るなど自分が納得できる結果を残してくれています。好きな算数だけでなく、理科や社会、苦手な国語についても自分はここが出来ていないから、次はこんな事をやっていくと、自分で話してくれました。
何の為、誰の為にという根本的な部分をクリアにしてあげること。その上で何が必要なのか、自分で導き出せるよう支えてあげることが重要だと思います。これからも子ども達のために、何が必要なのかを自分で導き出せるように全力で関わり、支えていきます。

「楽しさが創りだす学び」
新地飛鳥(GKC)
GKCに3月から通ってくれている小1の女の子の話です。 「英語は成果が見えづらい」とよくいわれます。特に低学年では「聞く」・「話す」の2技能が学習の中心となるので、より成果を図りづらいです。
その子はフリータイムでネイティヴ講師とよく遊び、授業も真面目に受けてくれる模範的な生徒でした。本人も英語が楽しいようで、「毎日GKCに行きたい」と家で話しているとお母様から伺っていました。それでも、夏休み前までは自発的に英語を発することはありませんでした。子どもたちの自発的な発言が出るよう、講師・スタッフと声掛けやリピート練習をできる限り行っていました。
そして夏休みに入り、学校がないので、その子はほぼ毎日GKCに来て、1日中GKCで過ごすことが多くなりました。
すると、その子がある日突然、「How do I say “毛糸” in English?」と受付のカウンター越しに、私に質問しました。とても驚くと同時に、嬉しくて涙が溢れそうになりました。 このフレーズは毎日みんなで練習していましたが、低学年の子どもたちにとっては長い文章で、覚えるのが難しく、自発的に使う子どもはいませんでした。
その日以降、同じフレーズを使い質問をしたり、「May I go to the bathroom?」など、その他のフレーズも出てくるようになりました。周りの子どもたちにもいい刺激となって、全体的に自発的な英語の発言が増えました。保護者様やスタッフからも同じように、「成果を感じる瞬間に立ち会い、嬉しかった」と報告を多々受けました。子どもたちの成長を日々感じ、保護者様・スタッフと共有できる環境にとても感謝しています。

「行動へのきっかけ」
青木志穂(ゴールフリー)
4月の上旬のつい最近の話です。GF松井山手に配属されてから数名の子どもたちに入塾をしていただきました。その中で出会ったY君の話をします。
Y君には弟がいて、先に入会をしました。その手続きの際に何気なく、「ご兄弟はおられるのですか?」と聞くと、お母様から、 「実は高校2年生の兄がいて、毎日寝てばかりで心配しています。弟が塾に行くことになったから、Yも自分も行った方がいいかも…と気になっているみたいなのですが…。私が言っても、絶対に行かない!と、話を全然聞いてくれなくて…」 と、ご相談を受けました。そこで初めてY君の存在を知りました。私は、「一度Y君のお話を聞いてみたいです。塾が気になっているということは、何か悩んでいると思うので、Y君に私が話をする機会をくれると嬉しいなと言っていたとお伝えください」と言い、その日は終わりました。
すると数日後、Y君のお母様から、「今からYと行ってもいいですか?」と連絡があり、Y君を連れて塾に来てくださいました。Y君に、まずは「来てくれて、そして会ってくれてありがとう」とお礼を言ってから、「何か普段悩んでることはある?勉強以外でもなんでもいいよ!」と質問しました。するとY君は自分の頭の中にある考えや気持ちをたくさん話してくれました。
1年生の最後のテストが悪かったことをひきずっている、実はテスト前は寝てしまって勉強できなかったこと、お母さんに勉強しろと言われていつも反抗的な態度を取ってしまうこと、それについて本当はとても申し訳ないなと思っていること、実はすごく不安なこと…etc。
一生懸命思いを伝えてくれ、私はその間一言も発さず傾聴をし続けました。たくさん話してくれた中に、私は高校受験で第一志望に受かることができなかった過去のY君の姿を見つけました。あの時早く勉強していたらよかったと感じ、大学受験は絶対後悔したくないと思っていたみたいですが、高校生になり勉強が難しく、やる気も出ない、お母さんの気持ちに応えたいけれど、もやもやしている自分の気持ちを相談する人がいない、と投げやりになっていたそうです。
私は、今のY君が大学受験まで残されている時間や、合格する実力と今の力とのギャップの話や入試の制度の話、そして普段の勉強の計画の立て方の話をしました。そして話の締めくくりに、「あなたは、物事に真摯に向き合える人です。私は後悔したくない、頑張りたいと思うY君を全力で応援します」と伝えました。
帰り際には、連れて来られたY君ではなく、「塾に通いたい!俺、頑張れると思う! 先生に会えてよかった!」と言ってくれるY君に変身していました。そして次の日から毎日のように自習に来てくれています。 そんなY君は先日定期テスト前、笑顔で「最近数学が楽しい! 勉強もゲームをしてるより楽しくなってきた!」と話してくれました。そして、「実は、大学に受かったら先生と働きたいと思ってるんだ!」と言ってくれました。
この言葉を聞いた時、私はY君の人生に関われたことの喜びを感じ、この先コーチとしてY君が帰ってきてくれることが楽しみになりました。そしてこれからも、誠心誠意子どもたちと関わっていきたいと強く思いました。

「想いをクリアリングする」
多田恵(ゴールフリー)
入社して初めてかかわった生徒のお話です。私は中途採用で12月に入社し、1月から立花教室に勤務しておりました。その時に出会ったのが中3の男の子でした。彼は友達と自習に来ても勉強をしている子の邪魔をしたり、授業中もコーチの話を聞けない生徒でした。
そんな彼のことをもっと知りたいと思いました。何が彼をそうさせるのか。何を思っているのか。何でも構わないので彼のことを知ろうと、自習に来た時に1、2時間ほど世間話をしました。そこで色々な話をする中でなぜ勉強に集中できないかを教えてもらえることができました。
彼はサッカーをしていましたが、途中でけがに見舞われ思うように練習できなくなったこと。自分の代わりに試合に出るようになった友達がサッカーの推薦で高校が決まっていること。頑張ったところでまた何か邪魔が入ってしまうのではないかという不安。色々話してくれました。私はその話をただただ聞くことしかできませんでした。
彼に何をしてあげられるだろう。そう思いながら次の日を迎えました。すると彼は次の日から自習室で真剣に勉強を行っていました。理由を聞くと、「悩みを聞いてもらえてすっきりした。今から頑張っても間に合わないかもしれないけど、とりあえず頑張ってみる」と言ってくれました。
入試まであと2か月もなく、公立は難しいだろうと言われていた彼ですが、その気持ちを信じてカリキュラム組みを行い、毎日塾に来てもらうようにしました。そして見事公立高校に合格しました。
何か答えを必ず出し、導いてあげなければなければならない。そう思っていた私はそれ以前に大切にしなければならないことを彼とのかかわりで学ぶことができました。

「真正面から向き合う」
田村篤史(成基学園)
昨年度、学研教室にて担当した園生、I君の話です。中3の春から入園してきたその子は、片耳がほぼ聞こえず補聴器を付けていました。
入園当初は、それに対して気を遣っていた部分があったのですが、しばらくすると、I君は耳が聞こえないことを言い訳にして、目の前の辛いこと、大変なことから逃げている部分がある事に気付きました。ご両親も学校も、今まで耳のことを理由に、厳しく指導することが無かったのか、本人にとって、それを利用することが当たり前になってしまっていました。
中3の夏期講習会直前、その子のクラスをHからAに下げることが決定しました。本人は納得がいかない様子でした。しかし担任の先生との面談では口をつぐみ、気持ちを言葉にしないままで、誰かが「可哀そうな自分」に気を遣って助けてくれるのを待っていました。授業中もあからさまに不貞腐れ、ろくに予習もしないまま講習会に来ていました。
私は、中3合宿の直前にその子を呼び出し、話をしました。 「耳が聞こえないことは、勉強に集中できない理由にも、困難から逃げる理由にもならない。I君の成績に対して厳しい判断をした担任の先生こそが、最もI君という人間に真摯に向き合っていることに何故気づかないのか。」
その言葉がよっぽど悔しかったのか、I君はその日から目の色を変えて必死に勉強をするようになりました。その後、I君は無事志望校に合格し、卒園式では厳しく指導した我々に、感謝の気持ちを述べてくれました。
先日、I君の進学した高校の教頭先生から、こんな話をお聞きしました。 文化祭の内容に関する生徒会の会議で、教頭先生が「これぐらいの内容で妥協しておこう」というような意見を言ったところ、若干16歳のI君から、「教頭先生、そんなんじゃダメなんです。本当にやりたいことのためには、誰よりも自分に厳しくなければ」と説教されてしまったそうです。 これまで関わった生徒の中でも、特に「人は成長する生き物である」ということを実感させてくれた園生でした。

「共に学び、共に高めあう」
藤江由可(成基学園)
前年度の中3生は素直で勉強に対して真摯に取り組む子どもが多く、クラスにも一体感がありました。 最も私が感動したのは、自分の得意な教科を分からない友達に教える姿があちこちで見られたことです。「Aちゃん、ここ教えてー!」「Rくん、これって考え方合ってる?」など、授業の前や後に子どもたちが活発に意見交換し合う姿が見られました。
普段からこのように助け合って勉強する雰囲気ができていたこともあり、お互いを認め合い、尊重し合う姿勢もありました。「Yちゃんは数学が得意ですごいなぁ、また教えて!」「Mちゃんは国語めっちゃできるよね!わたしも頑張ろうと思う。」などといった承認の言葉が教室で飛び交うようになり、入試前にはみんなで合格しようとする一体感が生まれていました。
中3の最終授業。「このみんなで授業を受けるのもこれで最後かぁ。なんかさみしいなぁ。」「このメンバーで勉強できてよかったわ!」という子どもたちの言葉に涙が出そうになりました。
社会に出れば、ひとりで仕事をすることはほとんどありません。必ず誰かとコミュニケーションを取り、チームで働くことが基本になります。中3生が、勉強の中にも人とコミュニケーションする、誰かを認める、誰かと議論しながら問題解決していく、という社会性を自然と取り入れてくれている姿に頼もしさを感じました。
単に合格することや知識を得ることが目的ではなく、成基で学んだことや、立てた志が人生の礎となるよう、今後も子どもたちと関わっていきます。

「本音をぶつけあうこと」
比留田真由(ゴールフリー)
いつも人に対してきつい口調で話をしてくる高校3年生のYくんとお母さんとの三者面談の時の話です。面談が始まって早々に親子喧嘩に発展してしまいました。
お互いの言い分を聴いてみると、お母さんにとってはYくんの生活態度や、勉強に対する姿勢が不満になっている様子で、反対にYくんはご両親からの言葉がすべて叱責にしか聞こえないということが不満な様子でした。 この2人の間のコミュニケーションが不足していることは明らかでした。
お互いが思うことや感情をぶつけ合う時間が数十分続きました。そうはいえどYくんはまだ高校生です。最後には言いくるめられたという表情でうつむいて黙ってしまいました。Yくんの様子やお母さんとのやり取りを見て、私はすごく情けない気持ちになりました。Yくんのことを理解しようともせず、腫れ物に触るような気持ちで接していたということにはっきりと気づいたからです。
彼は本当は人の言葉や態度に敏感で、自信がなく、周囲の人に認めてもらいたい一心で強がる姿を見せていただけなのではないかと感じました。そして何とかして、Yくんに自信をつけてもらいたい一心で、私は、Yくんの良いところをいくつもいくつも承認の言葉にして伝えました。
最初は黙って聞いていたYくんとお母さんでしたが、いつの間にか二人とも、涙を流していました。それから、言葉を発してくれたのはお母さんでした。
「私たちには大学受験の経験がなく、正直不安で仕方がなかった。とにかく、できるようにさせなきゃ、と自分の考えばっかり押し付けて本人のことを見ていなかった。よその子は立派で、なぜ我が子だけが勉強や基本的な生活すらできないんだとずっと思っていた。でも違いましたね。頑張っていたんですね。もちろんこの子自身もまだまだいろんなことを頑張らないといけないとは思う。そして、私たちもこの子のことをしっかりと見守っていかなきゃいけないと思う。で、Yはどうしたいの?」と聞いてくださいました。
それからYくんが思っていることを安心して少しずつ話し始めてくれました。承認することの力強さを感じた瞬間でした。